岩手県立中部病院伊藤です。
当HP中のスタッフ紹介に「認定医一覧」のページがございますが、泌尿器科専門医を取得後にサブスペシャルティ領域(基本領域の専門医を取得した後に目指す、専門的で範囲の狭い専門医)が取得できます。私自身2017年に泌尿器科専門医を取得し、その後は1年に1個なんらかの認定医・専門医を取得することを目標に、これまで「日本がん治療認定医機構 がん治療認定医」・「日本透析医学会 透析専門医」・「日本腹膜透析医学会 認定医」・「日本急性血液浄化学会 認定指導者」を取得いたしました。泌尿器科専門医以外のサブスペシャルティ領域の専門を取得することは泌尿器科一般以外の知識・技術を習得する以外にも、後進の指導や認定施設の維持など医局の発展のために重要なことであると考えます。特に当講座は腎不全・透析領域も担当しており岩手医科大学附属病院を中心に認定施設も多く、広くサブスペシャルティを取得することができます。また一つの専門医を取得することで付帯する認定などもありさらに幅を広げることも可能です。
今後サブスペシャルティ領域の認定を取得する方のために代表的なサブスペシャルティ認定の取得方法などご紹介したいと思います。
〇 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
申請要件
(1)がん治療認定医:日本国の医師免許証を有すること。
(2)がん治療認定医:所属する基本領域の学会※の認定医又は専門医の資格を有すること。
(3)以下のいずれかに準拠した緩和ケア研修会を修了していること。
がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(厚生労働省健康局長通知)
がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針(厚生労働省健康局長通知)
4)本機構の定める認定研修施設において、本機構の定める『研修カリキュラム』に基づくがん治療研修(通算2年以上のフルタイム研修、ただし2年間の初期研修期間を除く)を修了し、指導責任者による証明がなされていること。 担当医としてがん治療を実施したがん患者のうち20例(予備を含め25例まで申請可)の症例一覧を提出する。
(5)2019年1月1日から審査申請時までの期間に下記の業績を有すること。
- 学会発表「がん診療」についての業績2件(予備を含め5件まで申請可)
- 論文発表「がん診療」についての業績1件(予備を含め3件まで申請可)筆頭・共同は問わない。
(6)本機構が開催する教育セミナーに参加し、認定医試験に合格していること。
(7)2019年1月1日から申請時までの期間に下記学術単位を合計で20単位以上取得していること。
コメント:泌尿器科の診療および学会発表など通常行っていれば申請可能です。試験内容も事前に購入するセミナーの参考書から出ますし、試験前は1日半かけてみっちりセミナーを聞いて試験に臨みます。泌尿器科以外の癌領域や緩和領域などの知識も取得することができます。教育セミナー受講、認定試験受験は専門医取得前でも可能です(試験合格は5年間有効)。当講座のサブスペシャリティ領域では最も多く取得されています。
取得者:小原 航、杉村 淳、髙田 亮、兼平 貢、前川 滋克、加藤 廉平、五十嵐 大樹、伊藤 明人
〇日本泌尿器内視鏡学会・ロボティクス学会 泌尿器科腹腔鏡技術認定医
申請要件
(1) 日本泌尿器科学会専門医である。あるいは、日本専門医機構が認定する泌尿器科専門医である。
(2) 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会会員である。
(3) 腹腔鏡下腎摘除術(用手補助下を含む)、腹腔鏡下副腎摘除術、ロボット支援腹腔鏡下腎摘除術、ロボット支援腹腔鏡下副腎摘除を独力で遂行できる技術を持っている。
(4) 腹腔鏡下腎尿管手術(用手補助下を含む)、腹腔鏡下副腎摘除術、ロボット支援腹腔鏡下腎摘除術、ロボット支援腹腔鏡下副腎摘除、あるいはこれらに準じる泌尿器腹腔鏡手術を、主たる術者として20例以上執刀した経験がある。
(5) 日本泌尿器科学会、日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会、日本内視鏡外科学会が主催する、あるいはこれらの学会が公認する、腹腔鏡に関する教育セミナーに参加している。
付帯資格
日本内視鏡外科学会技術認定[泌尿器腹腔鏡]
第20条
日本泌尿器科学会/日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会泌尿器腹腔鏡技術認定証の交付を受けた者は、その認定証と申請料を添えて、日本内視鏡外科学会技術認定制度委員会に、日本内視鏡外科学会技術認定[泌尿器腹腔鏡]の認定を申請することができる。ただし、この申請を行う者は日本内視鏡外科学会会員でなければならない。
コメント;現在泌尿器科手術は腹腔鏡、ロボット手術が中心になっており、今後ますます重要になってくる認定資格で、当講座ではがん治療認定医と並んで取得している先生が多いです。
取得者:小原 航、高田 亮、兼平 貢、加藤 陽一郎、加藤 廉平、前川 滋克、松浦 朋彦、藤島 洋介
〇日本透析医学会 透析専門医
申請要件
1)日本国の医師免許証を有し,医師としての人格および識見を備えていること.
2)日本内科学会および日本外科学会において定められたいずれかの認定医または,専門医,日本泌尿器科学会,日本小児科学会および日本救急医学会において定められたいずれかの専門医,もしくは日本麻酔科学会において定められた指導医の資格を有し臨床経験5年以上を有していること.なお,初期研修医1年目は臨床経験に含めない.
3)本学会の専門医制度委員会の規定によって編成された研修カリキュラムに従い,学会認定施設において1年以上または教育関連施設において3年以上を含む通算3年以上を主として透析療法に関する臨床研修を行いかつ業績のあること.なお、勤務日数は、原則週4日以上を研修1年と認定する.ただし、週3日の勤務は、研修1年の4分の3に相当し、週2日の勤務は、研修1年の4分の2に相当する.週1日のみの勤務は研修期間として認めない.
4)専門医制度規則施行細則に示されている業績基準を満たしていること.
本学会年次学術集会参加 1 回以上
筆頭者として学会発表 1 件以上行っており,かつ論文 1 編以上を含むこと.ただし,論文は共著でも可とする.
5)専門医認定の試験および審査において適格と判定され,専門医として登録を完了した者であること.
6)申請時において,本学会の会員歴3年以上であること.
必要症例数(認定施設・教育関連施設の症例に限る、レポート作成)
A 維持透析症例 6 例
B 慢性腎不全透析導入症例 3 例
C 急性腎不全血液浄化症例 2 例
D 血液透析装置組み立ておよび操作症例 1 例
E バスキュラーアクセス作製症例(手術助手や手術見学を含む) 1 例
F バスキュラーアクセスカテーテル留置症例 1 例
G 透析症例剖検例または死因検討例 1 例
H その他の血液浄化法(血漿交換,吸着,顆粒球除去など) 2 例
I 腎移植症例(移植手術の見学,移植の情報提供含む) 1 例
計18 例
付帯資格
日本腹膜透析医学会 認定医
1.認定医は次の各項の資格をすべて満たす者であること
1)日本国の医師免許証を有し,医師としての人格および識見を備えていること
2)基本領域専門医資格は問わないが,臨床経験5年以上を有していること
3)申請時において,本学会の正会員であること
4)申請時において,一般社団法人日本透析医学会の専門医を有すること,または連携認定医を3年以上務めていること
5)申請時において,本学会学術集会・総会に過去3回以上参加していること
6)申請時において,腹膜透析に関する発表を過去5年間で1件以上,もしくは論文(基礎的・臨床的研究あるいは症例報告でも可)1編以上の業績があること(いずれも筆頭者でなくても可)
腎代替療法専門指導士
看護師・保健師, 管理栄養士, 薬剤師、臨床工学技士、移植コーディネーター、および医師の資格を有するもの。 応募時にそれぞれの専門(または認定)資格を取得している者
腎代替療法選択指導に関する20単位(1単位50分)のe-ラーニング講義の受講を行い、各受講単位のe-ラーニング試験に全5問に正解すること(試験は複数回の受験は可能)(*)
日本腎臓学会、日本透析医学会の専門医及び日本腹膜透析学会、日本臨床腎移植学会の認定医
コメント:透析専門医取得には3年以上の実績+学会入会、学会発表・論文、18症例のレポート、認定試験合格など取得までは準備を進めることが多いですが、レポート作成のための認定施設・教育関連施設の施設認定には常勤の透析専門医が必要です。導入期加算や腎代替療法管理指導料などの要件に腎代替療法専門指導士が必要になっておりますます重要になってくると思います。
取得者:阿部 貴弥、伊藤 明人、佐藤 一範、久野 瑞貴
〇日本臨床腎移植学会 腎移植専門医
申請要件
1)日本国の医師免許を有すること
2)卒後6年以上で内科系は日本内科学会認定内科医または総合内科専門医、日本小児科学会専門医のいずれかの資格、外科系は日本外科学会認定医、専門医または指導医、日本泌尿器科学会専門医のいずれかの資格を有すること
3)日本臨床腎移植学会入会月から申請時まで引き続いて3年以上(満3年)会員であること
4)学術集会に1回以上の参加かつ学術集会教育セミナーに1回(2単位)以上の参加があること(学術集会教育セミナーに参加が不可能な場合は集中教育セミナーに1回(3単位)以上の参加で代用することが出来る)
5)外科系は通算3年以上臨床腎移植医療の外科的修練を、内科系は通算1年以上臨床腎移植医療の内科的修練を行い、必要な経験と学識技術を修得する
6)業績として臨床腎移植関連の学会・研究会の発表または論文または著書があること
7)医療倫理を尊守していること
外科系専門医診療実績(必須手技の経験数と経過報告)
1)ドナーの適応としての留意点5例
2)レシピエントの適応としての留意点5例
3)腎移植術と腎採取術の術者または助手の経験が合計して10例以上(生体・献腎、期間は問わない)とし、少なくとも腎移植術の術者の経験が5例以上あること
4)術後4週までのレシピエントの経過報告5例
以上4項目について、1)、2)、4)は各項目ごとに5例を簡潔に記載する
業績(内科系および外科系も必須)
1)腎移植に関する論文1編以上(共著者でも可)
2)学会または研究会で発表、1回以上(少なくとも1回は筆頭演者、2回目以上は共同発表者でも可)
3)論文と学会/研究会発表の合計が4つ以上(例:論文1+発表3、論文2+発表2、論文3+発表1)であること
※以上の業績は様式4を参照する。
※自家腎移植は業績として認めない
コメント:現在岩手県で腎移植を行っている施設が少ないため取得できる施設は限られますが、腎移植は血液透析・腹膜透析と合わせて腎代替療法として説明することが推奨されています。導入期加算や腎代替療法管理指導料の算定要件にも移植患者の数が必要であり、腎移植に関して知識を深めていくことは重要です。
取得者:杉村 淳、松浦 朋彦
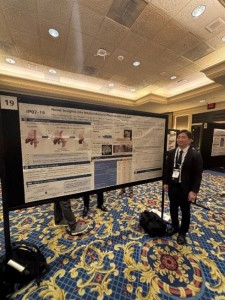
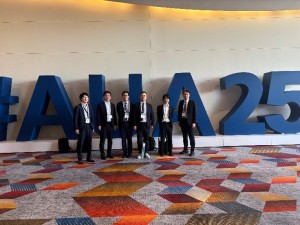



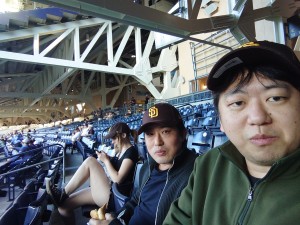



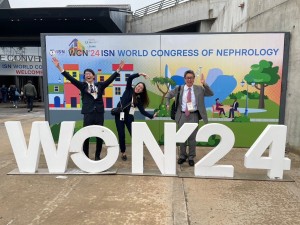 会場前での記念撮影
会場前での記念撮影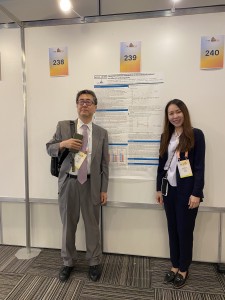 関口先生ポスター
関口先生ポスター






最近のコメント